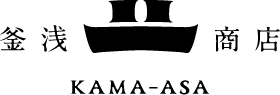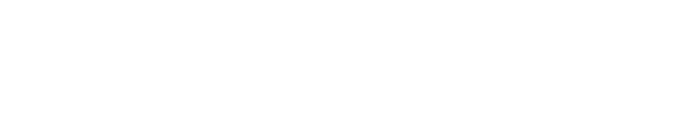コサカ金網のステンレス網付属の「釜浅の炭火焼き台」の詳細はこちら

- TOPICS
-
- TOPICS 01始まりは銀杏煎り。きっかけはなんと飛び込み営業!
- TOPICS 02より安全に、より丈夫に、より美しく。改良の背景の細かなこだわり
- TOPICS 03父が立ち上げた工場を26で承継、夫婦二人三脚で発展させる
- TOPICS 04圧倒的に丁寧な仕事から生まれる高い品質への信頼
つくる人コサカ金網

- 1966年に現社長・小坂実さんの父が創業。1980年にエアー式スポット溶接機を2台導入し、1983年より大阪・千日前道具屋筋商店街に商品を卸すように。1996年より長男の実さんが事業を承継し、事業を拡大。現在は実さんと妻の智奈さんの夫婦2人で工場を営んでいる。コサカ金網 公式サイト
TOPICS 01始まりは銀杏煎り。きっかけはなんと飛び込み営業!
釜浅商店で扱う焼き台や七輪の上に載せる焼き網や、天ぷらやフライをする時に使うカス揚げなどは、丈夫で錆びにくく、寿命も長いステンレス製のもの。それらをお願いしているのがコサカ金網の小坂さん夫妻です。お二人の拠点は平野区の中でも多くの町工場が操業する加美地域の工場。スポット溶接機械2台が鎮座する細長い空間で、黙々と作業が進みます。

上からぶらさがっているのはさまざまな型。型はもちろん、完成品も1個多く作って保管したり、写真を撮っておいたりして、再び作ることになった時に困らないようにしている。
釜浅商店とコサカ金網のお付き合いは2012年頃にスタート。最初にお願いしたのは銀杏煎りでした。
小坂さん
当時は僕らも大阪しか知らんかった。で、もっと遠くでも僕らのことを知ってくれたらええのにな、と思って、鞄の中にいっぱい道具を詰めて合羽橋に行ったんですよ。最初に入った店で「アポもなしに普通に来て話を聞いてくれる人間なんておらんで」って言われて。そうなんや、ありがとうございますって言って、とりあえずいろいろ回ったんですけど、ほんまにもう、「うちとこは新潟から取ってるから」とか、そんなんばっかりで。
和田
そうだったんだ。何軒くらい回ったんですか?
小坂さん
20軒くらいですね。でも、ほんまに全く話すら聞いてもらえなかった。もう帰ろうかな、と思った時に、たまたま釜浅さんに入ったんです。そしたら、ちょうど社長のお母さんがお店に立ってはって、「僕ら大阪で網屋やってるんです、こんなん作ってるんです」って言ったら、めちゃくちゃ親切に聞いてくれて。それで、「うちの社長も今、ちょうどこういうのを探してるんです」って、京都で買って来られたっていう銀杏煎りを見せてくれたんですよ。

丈夫で使いやすい銀杏煎り。銀杏が思い切り爆ぜてもびくともしない。(2025年現在は受注生産品)
和田
その場でお見せしてたんですね! 知らなかった。
小坂さん
それでね、見た感じでどういうものかわかったから、大阪に戻ってすぐ、うちのやり方で作ってみて、「話を聞いていただいたお礼に」って送ったんです。そしたら、社長からすぐに電話がかかってきて。そこからのお付き合いで今に至る、という感じです。
和田
僕も、小坂さんから送っていただいた銀杏煎りを熊澤が見せにきた時のことは覚えてます。「これ見て。こないだ買ってきたのとは全然違うよね、こっちの方が良くない?」って言われて、僕も「いいですね、やりましょう、やりましょう!」って。それで始まったんですよね。
小坂さん
銀杏煎りは昔、もうちょっと大きいものを鉄で作っとったんですわ。だから、あれをパッとみせていただいた時に「なんでこんなややこしい作り方しとんのやろ?」と思ったんですよね。そこから他の商品にも広がっていきましたよね。

TOPICS 02より安全に、より丈夫に、より美しく。改良の背景の細かなこだわり

和田
そうです。小坂さんから見せてもらって採用したもののひとつがカス揚げ。それまで扱ってきたカス揚げって、洗う時に網がスポンジに引っかかったりするやつばっかりで。まあ、カス揚げって一般的には300円とか400円くらいのものだから、しょうがないんですけど。
小坂さん
そうですね。それに対して、うちのは当時でも1200円くらいしましたから。だから、もともとカス揚げはあんまり数が出ないし、そんなに作ってなかったんです。ところが、釜浅さんで紹介してもらったら、ホテルの厨房などで使われるようになった。これにすれば手が危なくないから、って。
和田
本当に、小坂さんのカス揚げは安心して使ってもらえるんですよ。それで焼き網もお願いするようになったんです。焼き網って、枠にちゃんとくっついてないところとかがあっても、「別に使えるんだからそんなところにこだわらなくてもよくない?」って感じがあって。それがね、小坂さんに頼んだら全く違うんですよ。よく見ないとどこで溶接されているかもわからないくらい美しいし。もちろん値段はちょっと高いけど、熊澤も「もうこれにしよう」って。小坂さんなら一発でいいものが上がってくるので。それで、結局全部小坂さんにお願いすることにしたんです。ちょうどうちでも七輪や焼き台が増えてきた時期で、それに合わせて網をどんどん作ろうということになって。今、定番だけでも結構ありますよね。
小坂さん
6種類ぐらいは常にあるかな。最盛期は多分8種類ぐらいあった。

焼き網には丈夫なクリンプ織の金網を採用。細部まで丁寧に仕上げてあるので、金網がほつれることもなく安全。

せいろとセットで購入する方の多い「せいろ用 すのこ網」。こちらの金網は平織のもの。
和田
あと、今一番出ているのが、中華せいろに合わせて使う「せいろ用 すのこ網」。
小坂さん
ああ! あれは当初、そんなに売れると思ってなかったんですよ(笑)。
和田
あれはめちゃくちゃ好評なんです。今、せいろを買う方の7割ぐらいがあの網を一緒に買ってくださると聞いています。
小坂さん
最初は「誰がこんなの買うんやろ?」って思ったんですけど、考えてみればなかなかのアイデア商品ですよね。
和田
たくさんのものをいっぺんに蒸したいとき、せいろを2個買うと嵩がすごくなってしまうし、収納にも困るので、せいろ自体を深くして、中で2段に分けられたらいいなと思っていたんです。それで、どうやって2段に分けようかと考えた時に「やっぱり金網だな、小坂さんに相談したら何とかしてくれるだろう」と思ったんですよね。そしたら、完璧なもの、いや、それ以上のものを作っていただけて。小坂さんが提案してくれたことは、だいたい「はい、じゃあそれでお願いします!」って感じなんです(笑)。
TOPICS 03父が立ち上げた工場を26で承継、夫婦二人三脚で発展させる
コサカ金網が誕生したのは、1966年(昭和41年)のこと。小坂さんのお父様が一人で立ち上げた会社です。

「実際に会ってご相談したほうが話が早いし、来られる限り大阪まで来ちゃいます! 小坂さんに会いたくなっちゃって」と和田。小坂さんも思わず苦笑い。
小坂さん
元々親父はこの仕事で大阪のミナミの方に奉公に行ってたんですが、そこから独り立ちする形でここを立ち上げたみたいです。僕は一応、高校を卒業して別の会社に就職したんですが、結局親父からすぐに「忙しいからもう帰ってこい」って言われて。こっちもずっと親父の仕事を手伝ってきたから、すぐ仕事はできましたしね。
和田
へえ、そうなんですか。お手伝いしていたのはいつ頃からですか?
小坂さん
小学校の頃からですね。僕と弟が学校から帰ると、いつも「おやつ買うたらすぐ工場に来い」みたいな手紙とともに100円玉が置かれとって。それでずっと、網を切ったり、針金を切ったりみたいなことを手伝ってた。溶接は中学くらいからかな。だから、工業高校に入ったあとも、最初から溶接は全然できたんですよ。
和田
そうなんだ、すごいなあ。で、最初はお父様と。
小坂さん
そうです。といっても、親父は病気をして僕が26の時に亡くなったんですけど。そこからは母親と2人でやるようになって、その後嫁さんが手伝ってくれるようになって。夫婦2人でやるようになって、もう20年くらいになります。うちは子どもたちも後を継がないので、今後も2人です。息子は金属アレルギーなんですよ。ここに手伝いに来る時もゴム手袋をさせているんです。
和田
そうなんですか……それは大変すぎる。ところで、弟さんはどうされたんですか?
小坂さん
弟は全然違う会社です。母親が「兄弟でやったらあんまりうまくいかんやろ」言うて。弟も全部できますから、いざとなったら呼び寄せますけど、普段はバラバラです。

工場に並べられたステンレス棒。「材料は東大阪の会社から仕入れることが多い。金属加工だけでもいろんな工場があるんですよ」と小坂さん。
和田
そうなんですね。それはそうと、小坂さんがこれまで作ってこられたものの中で一番大変だったもの、苦労されたものは何ですか?
小坂さん
うーん……大変という意味でいったら、和菓子屋さんが小豆を炊く用の巨大な鍋にぴったり合う籠(小豆煮籠)ですかね。豆が均一に炊けるように、籠の真ん中に同じ網で作った筒状のものが取り付けてあるんですけど、これが大変で(笑)。サイズが大きすぎるし、数も出ないので型がなく、まず段ボールで型を取ってから形を作っていくんですよ。
和田
うわー、それは大変だ。でも、それだったら、うちにもそういう案件で寝かせたままのものがあるので、お願いすることになると思います! 甘納豆の籠(納豆籠)で、昔作っていた工場では「もう作れない」って言われたんですよ。昔のものが倉庫にあるので送ります(笑)。
TOPICS 04圧倒的に丁寧な仕事から生まれる高い品質への信頼
焼き網は、ステンレスの丸棒で作った枠に、同じくステンレスのクリンプ織金網(注:波型に加工した太い金属線を縦横に組み合わせた金網。一般的な平織金網に比べて強度が高い)をアルゴン溶接(注:タングステン電極を用いたアーク溶接の一種。精密な溶接に向く)して作ります。枠と網の端を丁寧かつリズミカルに溶接することで、すっきりと美しく仕上げているのが特徴です。ステンレス枠のスポット溶接(接合する金属の接触部分に電極を当てて局所的な高電流を短時間流し、金属を溶融させてて都合する方法)は智奈さんが行っています。

枠の部分のスポット溶接は智奈さんの仕事。

金網の端は一ヵ所ずつアルゴン溶接で固定。
和田
これ、溶接も本当に綺麗なんですけど、焼き台にのせた時に網がずれないように、一番外側の網を凹ませてあるのがすごいんですよね。これ、僕はガシャッといっぺんに凹ませる機械か何かでやっていると思っていたんですけど、実際は小坂さんが1本1本叩いていた。びっくりでした。
小坂さん
まあ、こういうのができるすごいプレス機械とかもあると思うんですけど、うちはこんな原始的なやり方なんで、1日50枚が限界。腕がパンパンになります。でも、肉を焼いてる時に網がずれたら、嫌な気分がするじゃないですか。自分が買わないようなものは作りたくないですからね。

溶接が済んだ焼き網の内縁を金槌で叩き、焼き台にのせた時に網がガタガタ動かないように窪みをつけていく。
和田
日本製の焼き網でもこのくらいの品質のものはない。基本的に、網を洗うのが面倒だという人が多いので、今は使い捨てできる品質の網が多くて。でも、この網だったら酷い汚れは焼いて落としてしまえばいい。それでも大丈夫なくらいしっかりしているので、長く使えるんですよね。
小坂さん
そうなんですよ。焼き落としてもらって全然大丈夫です。
和田
とにかくね、小坂さんに任せておけば間違いないっていうのが嬉しくて。何か新しいものをお願いしても、「こんなのが上がってきたらいいな」と僕らが想像したもの以上の、120点のものが上がってくるから。

「どや!って感じで自信作を持っていっても、『そこ置いといて』みたいな感じ。釜浅さんはみんな褒めてくれるんで、照れくさいけど嬉しいですね」と話す小坂さん。
小坂さん
釜浅のみなさんは、お世辞でも褒めてくれるんです。ちょっと恥ずかしいなと思いつつも、やっぱり仕事のモチベーションはめちゃくちゃ上がります。いいものを作ろう!って気持ちになりますよね。
和田
とんでもないお願いをして断られることもありますけどね(笑)。絶対に量産が難しそうなものとか。それでも、小坂さんは基本的に「ここの部分をこうしたらできるんじゃないですか」って返してくれる。だからこっちも「時間は全然かかっても大丈夫ですよ、僕らは待つので」って、小坂さんが断りにくいような感じでお願いしちゃう(笑)。
小坂さん
普段からちょこちょこと話してもらえるのがいいですよね。
和田
そんなふうに言ってもらえるので、また甘えてしまいそうです。これからもよろしくお願いします!

小坂さんご夫妻とともに。色違いのデニムのエプロンの胸ポケットにあるコサカ金網のロゴマークは、お子さんが入れてくれたのだそう。

2児の父で、休日は釜浅の道具を使い家族に料理を振る舞う。趣味は筋トレ・格闘技(MMA)・サウナ。
執筆・編集:山下紫陽 撮影:釜浅商店